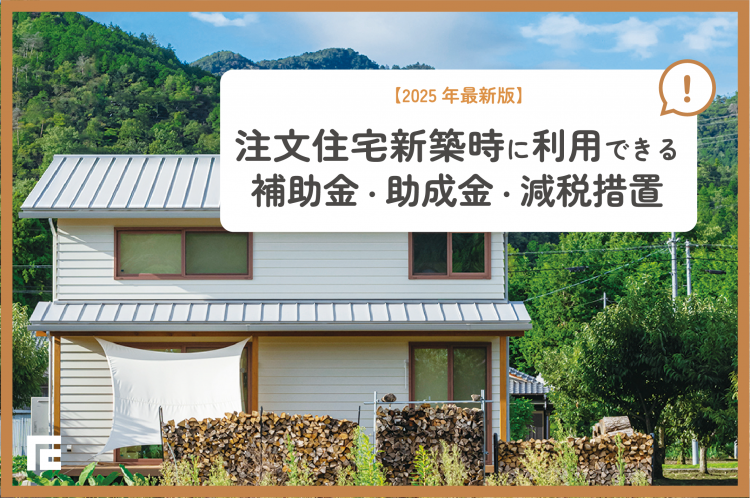税金・維持費
注文住宅には固定資産税がいくらかかる?計算方法や、安くするポイントも紹介
更新:2025.12.02 公開:2025.11.05
注文住宅は「買ったら終わり」ではありません。固定資産税という税金を毎年払っていく必要があります。
初めてマイホームを購入する方は
「固定資産税がいくらかかるのか」
「安く済ませる方法はないか」
など、気になってしまうことも多いでしょう。
この記事では、固定資産税の計算方法・安く済ませるポイント・支払い時期・方法などを紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
固定資産税とは?

固定資産税は、家を持ち続ける限り払う必要がある税金です。
土地の場所・状態・建物の状況などで大きく変わりますが、逆に、仕組みを知っておけば支払いの不安を減らせます。
ここでは、この固定資産税について説明します。
固定資産税の目安額
固定資産税の金額は、物件の評価額に1.4%をかけるのが基本ルールです。
たとえば評価額が2,000万円なら、年間28万円ほどが目安になります。
ただし、これはあくまで一例で、実際の税額は地域によって変わってきます。
都市部のように地価が高いエリアでは同じ広さの土地でも評価額が上がるため、税額もその分高くなりがちです。
一方、地方では同じ規模の土地を持っていても税額が抑えられるケースも少なくありません。
さらに住宅用地には「小規模住宅用地の特例」など軽減措置が適用されることがあり、実際に支払う金額は単純な計算よりも低くなることが多いです。
つまり、固定資産税の目安は一律に語れないものの、評価額の仕組みや特例の有無を知っておくと、どれくらいの負担になるかイメージしやすくなるでしょう。
注文住宅の固定資産税の計算方法
注文住宅を建てると、土地や建物の所有者として毎年固定資産税がかかります。
住宅ローンの返済や生活費に加えて毎年発生するランニングコストになることから、あらかじめ計算方法を理解しておくことが大切です。
また固定資産税は土地と建物は、それぞれ個別に軽減措置や特例が用意されています。
ここでは、土地と建物に分けて固定資産税の基本的な計算方法やその軽減措置、特例について解説します。
①土地
注文住宅の土地にかかる固定資産税は、以下の計算式で求められます。
土地の固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額) × 税率(1.4%)
固定資産税評価額は市町村が算定する金額で、購入時の公示価格の約7割が目安です。
さらに住宅用地には特例があり、課税標準額を大きく減額できます。
たとえば200㎡以下の部分は評価額の1/6に、200㎡を超える部分は1/3に軽減されるため、土地の広さによって負担額は大きく変わります。
300㎡の土地であれば、200㎡までが1/6に、残り100㎡が1/3に減額されて計算される仕組みです。
②建物
建物の固定資産税も、基本は土地と同じく以下の計算式です。
建物の固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額) × 税率(1.4%)
建物の固定資産税評価額は再建築価格の50%程度が目安です。
再建築価格とは、同じ建物を新たに建て直した場合に必要なコストのこと。
例えば3,000万円で建てた家であれば、評価額はおおよそ1,500万円となり、そこに税率1.4%を掛けることで年間21万円が課税額になります。
ただし、新築住宅には3年間(長期優良住宅なら5年間)、固定資産税が1/2になる特例があり、前述の例なら10.5万円に抑えられます。
注文住宅の固定資産税シミュレーション

注文住宅を建てる際、土地や建物の取得費用に応じて固定資産税がどのくらいになるのかを事前に把握しておくことは大切です。
特に、住宅ローン返済が始まる新築直後の数年間は、軽減措置が適用されるため実際の負担額がどう変化するかを理解しておくと安心でしょう。
ここからは、固定資産税のシミュレーションをしていきましょう。
土地1000万円、住宅2000万円の場合
まず土地から計算します。
土地価格1,000万円 × 評価率70% = 課税標準額700万円。
課税標準額700万円に住宅用地の軽減措置を適用し、200㎡以下のため評価額は1/6に圧縮されます。
よって、700万円 × 1/6 × 1.4% = 約1.63万円が土地の固定資産税です。
次に建物です。
建築費用2,000万円 × 評価率50% = 課税標準額1,000万円。
これに税率1.4%を掛けると14万円となりますが、新築住宅は3年間1/2に軽減されるため、実際の負担は7万円です。
したがって、土地と建物を合わせた最初の3年間の固定資産税額は、約1.63万円+7万円=8.63万円となります。
土地1000万円、住宅3000万円の場合
同じく土地は1,000万円 × 70% × 1/6 × 1.4% = 約1.63万円で変わりません。
建物は、建築費用3,000万円 × 評価率50% = 課税標準額1,500万円。
課税標準額1,500万円に税率1.4%を掛けると21万円です。さらに新築住宅の軽減措置で半額となり、3年間は10.5万円が課税額となります。
よって、土地と建物を合わせた固定資産税は、約1.63万円+10.5万円=12.13万円となります。
住宅2,000万円、3,000万円のシミュレーションからわかるように、土地価格が一定であれば、建物価格が1,000万円変わるごとに固定資産税は年間約3.5万円の差が出ます。
注文住宅の固定資産税を安くする方法

固定資産税は、注文住宅を建てた後に毎年かかる大きなランニングコストのひとつです。
しかし、制度の活用や家づくりの工夫次第で、その負担をぐっと抑えることができます。
ここでは、特例・減税措置の利用から、間取りや土地選びの工夫、さらに調査時の注意点まで、固定資産税を節約するための具体的な方法を解説していきます。
特例・減税措置を利用する
固定資産税を安くするために最も基本的で効果的なのが、特例や減税措置を活用することです。
住宅用地の特例では、200㎡以下の小規模住宅用地に対して課税標準額を1/6に軽減、200㎡を超える部分は1/3に軽減できます。
また、新築住宅については建物部分の固定資産税が原則3年間、半額に減額される制度があります。
長期優良住宅であれば5年間適用されるため、さらに負担が軽減されます。ただし、これらの特例や減額は自動で適用されるわけではありません。
役所への申告や条件の確認が必要なので、建てる前に制度の適用条件を把握してプランを調整することをオススメします。
延床面積を抑える
建物の固定資産税は評価額に基づいて算出され、その評価額は延床面積が広がるほど高くなります。
つまり、延床面積を適度に抑えることで、建築費用を減らしつつ固定資産税の負担も下げられるのです。
もちろん、狭すぎて暮らしにくい家では本末転倒ですが、使わない部屋や広すぎる廊下などを省き、コンパクトかつ機能的な設計にすることで効率的に節税できます。
最近では収納スペースを工夫して延床面積を抑えるケースも増えています。
快適性を維持しながらもムダを省いた設計を目指すことをオススメします。
地価の安い場所を選ぶ
土地にかかる固定資産税は、建物に比べると負担額は小さいです。
しかし、建物とは違い、年数が経過しても評価額が下がらないため、税額は長期間続きます。
そのため、土地の評価額が高い場合は、長期的に見ると負担が大きくなりやすいです。
そのため、地価が低い場所を選ぶのは、効果的な節税策の一つと言えるでしょう。
都市部より郊外や地方の土地は評価額が低い傾向にあるため、固定資産税を抑えつつ建物や設備に予算を回すことができますよ。
必要な設備・オプションを吟味する
注文住宅では床暖房や全館空調、外壁の高級素材など、豊富なオプションを追加できます。
しかし設備を増やすほど建物の評価額が上がり、固定資産税も高くなります。
「日常生活に直結しないオプションは減らす」選択をすれば、初期コストだけでなく毎年の税負担も抑えることが可能ですよ。
ただし、断熱性能や耐久性に直結する設備は長期的な光熱費削減や建物寿命の延長につながるため、慎重に取捨選択することをおすすめします。
長期優良住宅認定を受ける
長期優良住宅の認定を受けると、新築住宅に適用される建物の固定資産税軽減措置が3年間から5年間に延長されます。
耐久性・省エネ性能・可変性など厳しい基準を満たす必要がありますが、その分税制優遇が大きく、結果的に数十万円単位で節税できるケースも珍しくありません。
また、住宅ローン減税や補助金制度といった他の優遇措置とも組み合わせることも可能です。
固定資産税を抑えるだけでなく、家の価値を保つためにも、この長期優良住宅認定制度を検討する価値は大いにあります。
家屋調査に立ち会う
固定資産税額は、市町村の職員による家屋調査で決定されます。
この調査に立ち会わず、図面や書類だけで判断されると、実際より高い評価をされるリスクがあります。
たとえば、設計図上は高級仕様でも実際には標準グレードである場合、現場確認なしでは過大評価されやすいです。
そのため、家屋調査にはできるだけ立ち会い、担当者の質問には正確に答えるようにしましょう。
不要な設備が評価に含まれないよう説明するだけでも、結果として固定資産税を安く抑えられる可能性がありますよ。
固定資産税の納付時期
固定資産税の納付時期は自治体によって異なりますが、基本的には年4回の分割払いが一般的です。
納税通知書は4月~5月に発送され、各期ごとに納期限が設定されています。
例えば東京都23区では6月・9月・12月・翌年2月の4期払いですが、府中市は5月・7月・12月・翌年2月、岐阜市では4月・7月・12月・翌年2月と異なるスケジュールです。
同じ東京都内でも23区と府中市で納付月が違うように、自治体ごとに制度設計が異なるため注意が必要です。
払い忘れると延滞金が発生し、最悪の場合は差し押さえに至るケースもあるため、注文住宅を建てる前に居住予定地の納付時期を確認しておくことが大切です。
| 自治体 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 6月 | 9月 | 12月 | 2月 |
| 府中市 | 5月 | 7月 | 12月 | 2月 |
| 岐阜市 | 4月 | 7月 | 12月 | 2月 |
固定資産税の納付方法
固定資産税はさまざまな方法で支払うことができます。
市町村や金融機関の窓口で現金払い:納付書を持参すれば手続きは簡単。手数料も不要ですが、コンビニ払いには上限がある点に注意。
口座振替
事前登録した銀行口座から自動で引き落とし。払い忘れを防げるのが最大のメリットです。
コンビニ納付
仕事帰りや休日でも全国の主要コンビニで支払い可能。手軽さが魅力です。
スマホ決済
PayPayなど対応アプリでバーコードを読み取るだけ。近年急速に普及しています。
クレジットカード
支払い額に応じてポイントが貯まるためお得。ただし手数料が発生する場合もあるため、還元率との比較が必要です。
Pay-easy(ペイジー)
インターネットバンキングやATMから支払い可能。外出不要で済む点が便利です。
納付方法は豊富に用意されています。ポイントを貯めたい、支払いを忘れたくないなど、ご自分のライフスタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。
固定資産税とは長く上手に付き合いましょう

注文住宅を建てると、毎年必ず発生するのが固定資産税です。土地や建物ごとに評価額が算出され、軽減措置や特例を活用することで負担を抑えられる仕組みになっています。
固定資産税は一度払えば終わりではなく、長く続く住まいのランニングコスト。
家づくりと同じように計画的に考え、制度をうまく活用しながら無理のない形で上手に付き合っていくことが、快適なマイホーム生活を長く維持するカギになります。
グランハウスは岐阜/愛知/三重で注文住宅を提供している設計士集団です。
「ハウスメーカーでも工務店でもない、設計士とつくる」からこそ、お客様の想いやこだわりに丁寧に向き合い、ちょっとカッコいい、暮らしやすい家をご提案します。
施工実績は1,000件以上。「より良い家づくりをしたい」「岐阜で注文住宅を建てたい」とお考えの方は、ぜひグランハウスに一度お問い合わせください。