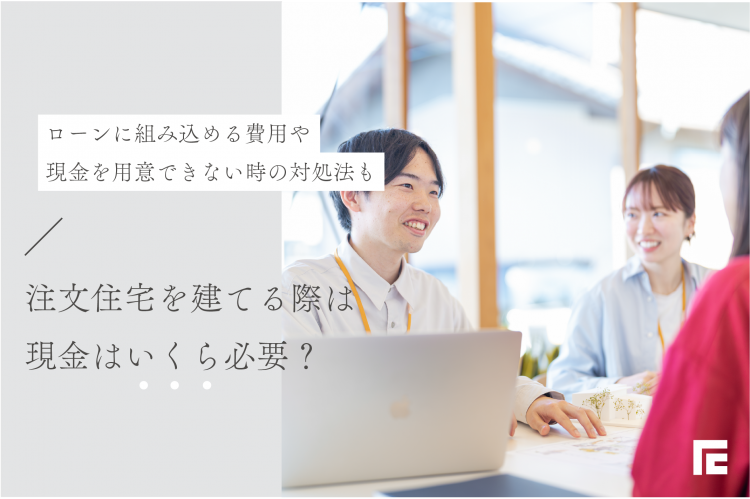費用・相場・ローン
注文住宅の費用シミュレーションを予算別に徹底解説|必要な事前準備やシミュレーションのポイントも
更新:2026.01.07 公開:2025.11.25
注文住宅は自由度が高い分、費用予測が難しいため、事前に無理のない資金計画や費用シミュレーションを行うことが重要です。
この記事では、注文住宅の費用シミュレーションを予算別に徹底解説します。
あわせて、必要な事前準備やシミュレーションのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
注文住宅を建てる際にかかる費用

注文住宅を建てる際には、「建物の費用」だけでなく、土地の購入や各種手続き・周辺工事など、さまざまな費用が発生します。
これらを把握していないと、予算オーバーになったり、思わぬ出費で計画が崩れたりすることもあります。
ここでは、注文住宅を建てる際に必要となる主な費用を4つに分けてわかりやすく解説します。
「土地の購入費用」「本体工事費用」「付帯工事費用」「諸費用」の順に、それぞれの内容と目安を確認していきましょう。
土地の購入費用
土地を持っていない場合、まず必要となるのが土地の購入費用です。
土地代はエリアや立地条件によって差があり、駅からの距離や周辺の利便性が高いほど高額になる傾向があります。
さらに、土地代そのもの以外にも登記費用・不動産取得税・仲介手数料などの諸費用が発生します。
- 登録免許税:課税標準額の1.5%(※土地の所有権移転登記の場合。建物の保存登記は0.4%)
- 不動産取得税:固定資産税評価額の3%
- 固定資産税:固定資産税評価額の1.4%(※新築住宅は3年間分の減額措置あり)
- 都市計画税:固定資産税評価額の0.3%(※自治体によっては課税されない地域もある)
- 司法書士報酬:5〜10万円程度
- 仲介手数料:土地代の3%+6万円(上限、※400万円超の場合))
- 手付金:売買価格の5〜10%程度
購入後は固定資産税などの維持費も継続的にかかるため、総予算を立てる際にはこれらを含めて検討することが大切です。
本体工事費用
本体工事費用とは、建物そのものを建てるための費用。注文住宅の総費用の約7割を占めるといわれています。
たとえば、総予算が2,000万円の場合、本体工事費はおおよそ1,400万円前後が目安です。
ここには、家を建てる上で必要な主要な工事が含まれます。
主な内訳は次のとおりです。
- 仮設工事:足場や仮設電気・トイレなどの設置工事
- 基礎工事:建物を支えるための土台をつくる工事
- 木工事:柱や梁など、家の骨組みを組み立てる工事
- 内装・外装工事:屋根、外壁、床、天井、壁などを仕上げる工事
- 設備工事:ドアや窓、水回り(キッチン・トイレ・浴室など)の設置工事
家の品質や快適性を左右する重要な部分のため、建築会社の施工実績や標準仕様を確認しておくことが大切です。
付帯工事費用
付帯工事費用とは、建物本体以外にかかる工事費のことです。
注文住宅全体の予算のうち、15〜20%が目安とされています。建物を建てるだけでなく、暮らしに必要な環境を整えるための工事が含まれます。
主な工事内容は以下のとおりです。
- 外構工事:駐車場・フェンス・門扉・庭など、建物の外回りを整える工事
- 引き込み工事:上下水道・電気・ガスを敷地内に引き込む工事
- 地盤改良工事:地盤が弱い場合に地盤を補強する工事
- 設備工事:照明器具・エアコン・カーテンレールなどの設置工事
- 解体工事:既存の建物を取り壊すための工事(建て替えの場合)
さらに、太陽光発電システムの導入や複数台分の駐車場整備などを行う場合は、追加費用が発生することもあります。
土地の状態や希望する設備内容によって金額が変わるため、見積もりの段階で確認しておくことが大切です。
諸費用
諸費用とは、土地代や建築費以外に発生するさまざまな手数料や税金などの費用を指します。
注文住宅の総予算のうち、おおよそ5〜10%程度が目安です。
建物の登記や住宅ローンの契約、引っ越し、家具・家電の購入など、家づくりの最後まで幅広く関係します。
主な諸費用の内容は以下のとおりです。
- 建物登記時の登録免許税:課税標準額の1.5%
- 不動産取得税:固定資産税評価額の3%
- 固定資産税:固定資産税評価額の1.4%
- 都市計画税:固定資産税評価額の0.3%
- 司法書士報酬:5〜10万円程度
- 印紙代:売買契約書や住宅ローン契約書に貼付
- 住宅ローン関連費用:事務手数料・保証料(金融機関によって異なる)
- 地盤調査費・地鎮祭費:数万円〜十数万円程度
- 引っ越し費用・家具・家電の購入費:内容や業者によって変動
諸費用は見落とされやすい部分ですが、住宅購入の最終段階でまとまった金額が必要になるため、事前に見積もりへ含めておくことが大切です。
注文住宅の費用シミュレーションに必要なこと

注文住宅を建てるためには、理想の家を思い描くだけでなく、現実的な費用シミュレーションの準備が欠かせません。
無理のない資金計画を立てることで、後から「予算が足りない」「思ったより費用がかかった」といったトラブルを防ぐことができます。
ここでは、注文住宅の費用シミュレーションを行う前に知っておきたい4つのステップを解説します。順に見ていきましょう。
「自己資金(頭金)」はいくらあるのか確認する
注文住宅の資金計画を立てるうえで、まず確認しておきたいのが「自己資金(頭金)」の金額です。
自己資金とは、すでに自分たちが保有している現金や預貯金、家族からの援助資金などを含む「自分で用意できるお金」のこと。
一般的には、住宅購入費全体の2〜3割程度を自己資金として準備しておくのが理想とされています。
住宅ローンを組む場合でも、「いくら借りられるか」よりも「無理なく返せる金額」に注目して、余裕をもった返済計画を立てることが大切です。
また、すべての貯金を頭金に充ててしまうのは避けましょう。住宅購入後にも、次のような資金を手元に残しておくことをおすすめします。
- 生活費の6か月分程度(急な出費や収入減に備えるため)
- 教育資金や老後資金(将来的な支出に備える)
- 自動車購入費や修繕費など(近い将来必要になる支出)
住宅ローンで借りられる金額を把握する
注文住宅を建てる際、多くの人が利用するのが住宅ローンです。
ローンを組むときに大切なのは「いくら借りられるか」ではなく「いくらなら無理なく返せるか」という視点です。
借入額の上限いっぱいまで借りてしまうと、家計を圧迫し、生活に余裕がなくなる可能性があります。
一般的に、年間返済額は年収の25%以内(上限でも30〜35%以内)が安全な目安とされています。
たとえば年収600万円の場合、年間返済額は約150万円、月々の返済額にすると12〜13万円程度が目安です。
住宅ローンには次のような金利タイプがあります。
- 固定金利型:金利がずっと変わらず、返済計画を立てやすい
- 変動金利型:金利が半年ごとに見直され、金利が低いときに有利
- 固定金利期間選択型:一定期間のみ金利が固定され、期間終了後に再選択が可能
また、返済方法にも次の2種類があります。
- 元利均等返済:毎月の返済額が一定で、家計管理がしやすい
- 元金均等返済:元金を均等に返済するため、利息が少なく済むが初期の負担が大きい
住宅ローンの返済額は、金利や返済期間によって変わります。各金融機関のシミュレーションを活用し「将来も安心して支払える金額」を目安に借入額を決めておきましょう。
建てたい家のイメージを決め、相場を調べる
自己資金やローンの目安がついたら、次は「どんな家を建てたいのか」を具体的にイメージします。
理想の家を形にするためには、間取り・デザイン・設備の3つをバランスよく考えるとよいでしょう。
間取り(広さ)を考える際は、必要な部屋数や生活動線をもとに検討します。
住宅費用は「坪単価 × 延床面積」(※ただし、付帯工事費・諸費用は別途必要)で決まるため、むやみに広さを求めると予算オーバーになりやすい点に注意が必要です。
一般的な目安として、1人あたりに必要な面積は約8坪前後といわれています。
たとえば4人家族なら約32坪ほどが目安ですが、最近では30坪以下でも快適に暮らせる間取りを工夫して建てる人も増えていますよ。
また、デザインや設備のこだわりも整理しておきましょう。
- デザイン例:シンプルモダン、和モダン、北欧風、ブルックリンスタイル、サーファーズハウスなど
- 設備例:アイランドキッチン、床暖房、太陽光発電、宅配ボックス、スマートホーム対応など
複数の施工事例やモデルハウスを見比べたり、希望と現実のバランスを取ったりしながら、自分たちの理想に近い家づくりを進めていきましょう。
家と土地にかかる費用の内訳を把握しておく
注文住宅を土地から購入して建てる場合、まず大切なのは「無理のない総予算の中で、土地と建物それぞれにいくら配分するか」を明確にしておくことです。
土地代と建築費を別々に考えるのではなく、総予算の中でバランスを取ることを意識しましょう。
一般的な目安には、土地3割・建物7割の割合が適正とされています。
たとえば総予算が4,000万円の場合、土地費用は約1,200万円、住宅の建築費用は約2,800万円が目安です。
この割合を意識することで、無理のない家づくり計画を立てやすくなります。
「立地条件や利便性を重視して土地に多くの予算をかけたくなる」という方も多いですが、土地費用をかけすぎると建物に充てられる予算が減り、理想の家を実現しにくくなることも。
失敗しないためには、次のような考え方がおすすめです。
- 総予算から建築費を差し引き、残りを土地費用として考える
- 建物の希望条件を優先し、土地の条件を柔軟に調整する
もちろん「多少高くても利便性を優先したい」という場合もあるでしょう。その場合は、土地購入費用を別途用意するなど、資金計画全体を見直すことが大切です。
費用シミュレーションに必要な情報
注文住宅の費用シミュレーションを正確に行うためには、まず自分たちの経済状況を把握しましょう。
どれだけの資金を用意できて、どれくらいの期間・金額で返済できるのかを明確にしておくことで、現実的で無理のない家づくりの計画を立てることができます。
ここでは、費用シミュレーションに必要となる5つのポイントを紹介します。
世帯年収
まずは、世帯全体の年収を正確に把握することから始めましょう。
世帯年収は、注文住宅の資金計画や住宅ローンの借入可能額を決めるうえで、最も重要な基礎データとなります。
夫婦共働きの場合や、親と同居している世帯では、収入がある全員の年収を合計して算出します。
会社員なら源泉徴収票の「支払金額」欄を、自営業やフリーランスの場合は確定申告書や納税証明書の所得金額で確認できます。
源泉徴収票や確定申告書が手元にない場合でも、自治体や税務署で「納税証明書」を発行してもらえば確認可能です。
年収の把握があいまいなままだと、ローン審査の想定や返済計画にずれが生じることがあります。家づくりの資金計画を立てる前に、世帯全体での正確な収入を確認しておきましょう。
現在組んでいるローン
注文住宅の資金計画を立てる際には、現在組んでいるローンの状況も正確に把握しておくことが重要です。
自動車ローンや教育ローン、カードローンなど、すでに返済中の借入がある場合、現在組んでいるローンの残債は住宅ローンの審査や借入可能額に直接影響します。
他のローンがあっても住宅ローンを組むことは可能ですが、年収に対する返済額の割合(返済負担率)が高すぎると、審査に通らなかったり、希望の金額を借りられなかったりするケースがあります。
また、審査に通ったとしても、他のローン返済が家計を圧迫し、毎月の返済負担が大きくなるリスクもあります。そのため、家づくりの計画を立てる前に、次の点をチェックしておきましょう。
- どの金融機関から借りているのか
- 残りの返済期間と残高はいくらか
- 毎月の返済額はいくらか
現在組んでいるローンを整理しておくことで、無理のない住宅ローン返済額を見極めやすくなります。
必要に応じて、他のローンをまとめて借り換えるなどの方法も検討し、安心して返済できる資金計画を立てましょう。
頭金として用意できる自己資金
注文住宅の費用シミュレーションを行う際には、頭金として用意できる自己資金の金額を正確に把握しておくことが大切です。
ここでいう自己資金とは、すぐに動かせる預金や現金、家族からの援助金などを含む「自分たちで準備できる資金」のことを指します。
この段階では、生活費や急な出費に備えるための貯蓄とは切り離して、実際に頭金に充てられる金額を明確にしておきましょう。
一般的には、住宅購入費用の2〜3割程度を頭金として準備できると安心とされています。
頭金の金額によって、借入金額や月々の返済額、ローン審査の通りやすさが変わります。
無理のない資金計画を立てるためにも、現時点で用意できる金額を正確に整理し、必要に応じて追加の貯蓄計画を立てておくとよいでしょう。
定年まで働ける期間
住宅ローンの返済計画を立てるうえで重要なのが「定年まであと何年働けるか」を把握しておくことです。
多くの金融機関では完済時年齢を80歳前後に設定していますが、理想的なのは現役で収入があるうちに完済することです。
定年後は収入が減るケースが多く、退職金でローンを一括返済できるとは限りません。
また、再雇用制度がある場合でも、給与が下がる可能性が高く、返済負担が重くなるリスクがあります。
そのため、ローンを組む前に次の点を確認しておきましょう。
- 現在の年齢と定年までの残りの勤務年数
- 定年後の働き方や収入見込み
- 退職金や年金などの受取予定額
これらを踏まえて、定年までに完済できる返済期間や、無理のない月々の返済額を設定することが大切です。
長期ローンを選ぶ場合でも、余裕があるときに繰り上げ返済を行うなど、計画的に完済を目指しましょう。
将来的な大きな出費
注文住宅の費用シミュレーションを行う際には、今後予定されている大きな出費も考慮しておくことが大切です。
住宅ローンの返済を長期にわたって続けることを考えると、将来のライフイベントにかかる費用を見込んでおくことで、無理のない資金計画を立てやすくなります。
たとえば、次のような出費も考えられます。
- お子さまの進学・教育費(高校・大学進学に伴う学費や塾代など)
- 車の購入や買い替え費用
- 家電・家具の買い替えや修繕費
- 老後の生活資金や住み替え費用
- 家族の介護費や医療費
あらかじめ将来の出費スケジュールをざっくり想定しておくことで、住宅ローンの返済額を決める際にも余裕を持たせることが可能です。
ライフステージの変化に合わせて見直しができるよう、貯蓄や投資などの備えも計画的に進めておきましょう。
【予算別】注文住宅の費用シミュレーション

注文住宅を建てる際は「どのくらいの予算で、どんな家が建てられるのか」を明確にイメージしておくことが大切です。
建物の広さ・仕様・デザインの自由度はもちろん、頭金の有無や住宅ローンの返済額によっても、実際に選べるプランは変わります。
ここでは予算別に注文住宅の費用シミュレーションを紹介します。
予算1,000万円台の注文住宅費用シミュレーション
予算1,000万円台で建てる注文住宅は、シンプルでコンパクトな住まいを希望する方に人気の価格帯です。
間取りを最小限に抑えたり、デザインや設備を工夫したりすることで、コストを抑えながらも快適な暮らしを実現できます。
ただし、本体価格が1,000万円ぴったりの家は現実的に難しいため、ここでは現実的なラインとして1,500万円・1,900万円の2パターンでシミュレーションを行います。
【試算条件】
商品タイプ:フラット35
借入期間:35年
金利タイプ:全期間固定
借入金利:全期間金利1.5%
ボーナス返済:なし
返済方法:元利均等返済
諸費用:試算に含まない
| 借入金額(建築費用+土地取得費用) | 返済額 | 年間返済額 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円(1,500万円+1,500万円) | 38,579,007円 | 1,102,260円 | 91,855円 |
| 3,400万円(1,900万円+1,500万円) | 43,722,964円 | 1,249,224円 | 104,102円 |
【参照】返済プラン比較シミュレーション(住宅金融支援機構)で試算
予算2,000万円台の注文住宅費用シミュレーション
予算2,000万円台になると、間取りやデザインの自由度がぐっと高まり、30坪前後のファミリー向け住宅も実現しやすくなります。
平屋・2階建てどちらのプランも選択肢が広がり、設備や内装にもこだわりを取り入れやすい価格帯です。
予算2,000万円台という価格帯では、快適さとコストのバランスが取りやすいのが特徴。
標準仕様でも十分満足度の高い住まいが建てられるほか、少し予算を上げることで高気密・高断熱住宅やデザイン性の高い外観なども検討できます。
ここでは、現実的なラインとして2,000万円・2,500万円の2パターンで住宅ローンの返済額をシミュレーションします。
【試算条件】
商品タイプ:フラット35
借入期間:35年
金利タイプ:全期間固定
借入金利:全期間金利1.5%
ボーナス返済:なし
返済方法:元利均等返済
諸費用:試算に含まない
| 借入金額(建築費用+土地取得費用) | 返済額 | 年間返済額 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|---|
| 3,500万円(2,000万円+1,500万円) | 45,008,901円 | 1,285,968円 | 107,164円 |
| 4,000万円(2,500万円+1,500万円) | 51,438,816円 | 1,469,676円 | 122,473円 |
【参照】返済プラン比較シミュレーション(住宅金融支援機構)で試算
予算3,000万円台の注文住宅費用シミュレーション
予算3,000万円台になると、間取り・デザイン・性能のすべてにおいてバランスの取れた理想の注文住宅を建てやすくなります。
外観デザインや内装の素材、住宅設備にもこだわりを反映しやすく、家族構成やライフスタイルに合わせた自由度の高いプランニングが可能。
予算3,000万円台という価格帯では、30〜35坪前後のゆとりあるファミリー向け住宅が主流で、ZEH住宅や高気密・高断熱仕様など、省エネ性能を重視した住まいを検討できるのも魅力です。
ここでは、現実的なラインとして3,000万円・3,500万円の2パターンで住宅ローン返済額をシミュレーションします。
【試算条件】
商品タイプ:フラット35
借入期間:35年
金利タイプ:全期間固定
借入金利:全期間金利1.5%
ボーナス返済:なし
返済方法:元利均等返済
諸費用:試算に含まない
| 借入金額(建築費用+土地取得費用) | 返済額 | 年間返済額 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|---|
| 4,500万円(3,000万円+1,500万円) | 57,868,729円 | 1,653,384円 | 137,782円 |
| 5,000万円(3,500万円+1,500万円) | 64,298,491円 | 1,837,104円 | 153,092円 |
【参照】返済プラン比較シミュレーション(住宅金融支援機構)で試算
予算4,000万円台の注文住宅費用シミュレーション
予算4,000万円台になると、40〜50坪前後のゆとりある注文住宅や二世帯住宅も現実的な選択肢に入ってきます。
間取りやデザインの自由度がさらに高まり、収納力のある広い間取りや、趣味・在宅ワークスペースを設けた理想の住まいを実現しやすくなります。
ただし、住宅ローンの返済負担も大きくなるため、無理のない資金計画が必須です。建築費だけでなく、土地代や諸費用、将来的なメンテナンス費用も含めてトータルでシミュレーションしておく必要があります。
ここでは、現実的なラインとして4,000万円・4,500万円の2パターンで住宅ローンの返済額をシミュレーションします。
【試算条件】
商品タイプ:フラット35
借入期間:35年
金利タイプ:全期間固定
借入金利:全期間金利1.5%
ボーナス返済:なし
返済方法:元利均等返済
諸費用:試算に含まない
| 借入金額(建築費用+土地取得費用) | 返済額 | 年間返済額 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|---|
| 5,500万円(4,000万円+1,500万円) | 70,728,386円 | 2,020,812円 | 168,401円 |
| 6,000万円(4,500万円+1,500万円) | 77,158,299円 | 2,204,520円 | 183,710円 |
【参照】返済プラン比較シミュレーション(住宅金融支援機構)で試算
注文住宅の費用シミュレーションのポイント
注文住宅を建てる際には、建築費用や土地代だけでなく、ローンの返済計画や長期的な資金の流れまで考えておくことが大切です。
どれだけ理想的な家を建てても、返済に無理が生じてしまうと安心して暮らすことができません。
そのため、費用シミュレーションでは「いくら借りるか」だけでなく「どのように返すか」「どんなリスクに備えるか」を具体的に考えていく必要があります。
ここでは、注文住宅の費用シミュレーションを行う際に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
無理のない返済額を把握する
注文住宅の費用シミュレーションを行う際には、まず「無理のない返済額」を把握することが重要です。
無理のない返済額を判断する目安となるのが、年収に対する返済額の割合(返済負担率)です。
一般的に、住宅ローンの返済負担率は25%前後が理想的とされています。
たとえば、年収が400万円の場合、返済負担率を25%とすると年間返済額は100万円(=月々約8.3万円)が目安です。
このように、年収から無理のない年間返済額を割り出すことで、借入可能額を逆算することもできます。
返済負担率が高くなりすぎると、生活費・教育費・将来の貯蓄が圧迫されるリスクがあるため「返せる金額」ベースで計画を立てることが大切です。
また、ボーナス返済を含めるかどうか、金利の変動リスクを考慮するかなども踏まえて、安定した返済ができる範囲を見極めておきましょう。
自分たちに合う金利タイプを選ぶ
住宅ローンの金利タイプは、総返済額を左右する重要なポイントです。
金利の種類によって返済額やリスクが変わるため、自分たちのライフプランに合ったタイプを選ぶことが大切です。
住宅ローンの主な金利タイプは次の3種類があります。
変動金利型
借入時の金利が低く、返済開始時の負担を抑えられるのがメリット。ただし、景気や金利動向によって将来的に返済額が増えるリスクがあります。
全期間固定金利型
返済期間中ずっと金利が変わらないタイプ。金利は高めですが、返済額が一定のため計画が立てやすく、長期的な安心感があります。
固定金利期間選択型(ミックス型)
一定期間だけ金利を固定し、その後に固定または変動を再選択できるタイプ。
短期間で見れば金利が低く抑えられますが、固定期間終了後の金利上昇リスクに注意が必要です。
金利タイプにはそれぞれメリット・デメリットがあるため、返済期間・収入の安定性・将来の金利動向を考慮しながら選ぶことが大切です。
長期的に見たときに「安心して返済を続けられるか」を基準に、自分たちに最も適した金利タイプを選びましょう。
無理して頭金を入れすぎない
頭金を多く入れるほど住宅ローンの借入額を減らせますが、無理をして貯金を崩しすぎるのは避けたほうが無難です。
たしかに頭金が少なすぎると審査に不利になる場合や、返済総額が増える可能性がありますが、生活資金まで切り崩してしまうと、突発的な出費に対応できなくなるリスクがあります。
理想的なのは、頭金を入れたあとでも「生活費の6か月分程度」を手元に残すことです。これにより、急な病気や修繕費、転職など予期せぬ出費があっても安心です。
一般的に、マイホーム購入時の頭金は物件価格の2割前後が目安とされていますが、年齢・収入・家族構成・今後のライフプランによって最適な金額は異なります。
「できるだけ多く頭金を入れたほうが安心」と思いがちですが、貯蓄を残す余裕も立派なリスク対策です。
長期的な家計の安定を見据えて、無理のない範囲で頭金を設定しましょう。
返済期間中のランニングコストも考慮する
注文住宅を建てる際は、住宅ローンの返済だけでなく、住み始めてから発生するランニングコストも忘れずに考えておきましょう。ローンの返済期間は長期にわたるため、その間にかかる維持・管理費を見落とすと、後々家計を圧迫する可能性があります。
具体的には、次のような費用が挙げられます。
- 固定資産税・都市計画税(毎年発生する税金)
- 外壁や屋根のメンテナンス費用(10〜15年ごとに必要)
- 給湯器やエアコンなどの設備交換費
- 内装リフォーム費(壁紙や床の張り替えなど)
- 火災保険・地震保険の更新費用
返済期間中のランニングコストを見込まずに住宅ローンの返済計画を立てると、思わぬ出費で家計が苦しくなることもあります。
そのため、将来的な維持費も含めた総合的な資金計画を立てることが大切です。
また、建材や設備のグレード選びを工夫して、メンテナンスコストを抑えられる仕様にするのもおすすめです。初期費用だけでなく、長期的なランニングコストを見据えた家づくりを意識しましょう。
注文住宅の資金計画にお悩みなら、グランハウスにお声がけください!

注文住宅の資金計画は「どれくらいの予算で、どんな家が建てられるのか」を明確にしながら、自己資金・ローン・将来の支出を総合的に考えることが大切です。
無理のない返済計画を立てることで、家を建てたあとも安心して暮らせる理想の住まいづくりが実現できます。
ただし、実際には「土地と建物のバランスをどう取ればいいのか」「住宅ローンはいくらまで組めるのか」「希望の間取りでいくらかかるのか」など、迷うポイントも多いもの。
そのようなときは、専門知識と実績を持つプロに相談するのが一番の近道です。
グランハウスは岐阜/愛知/三重で注文住宅を提供している設計士集団です。
「ハウスメーカーでも工務店でもない、設計士とつくる」からこそ、お客様の想いやこだわりに丁寧に向き合い、ちょっとカッコいい、暮らしやすい家をご提案します。
施工実績は1,000件以上。「より良い家づくりをしたい」「岐阜で注文住宅を建てたい」とお考えの方は、ぜひグランハウスに一度お問い合わせください。