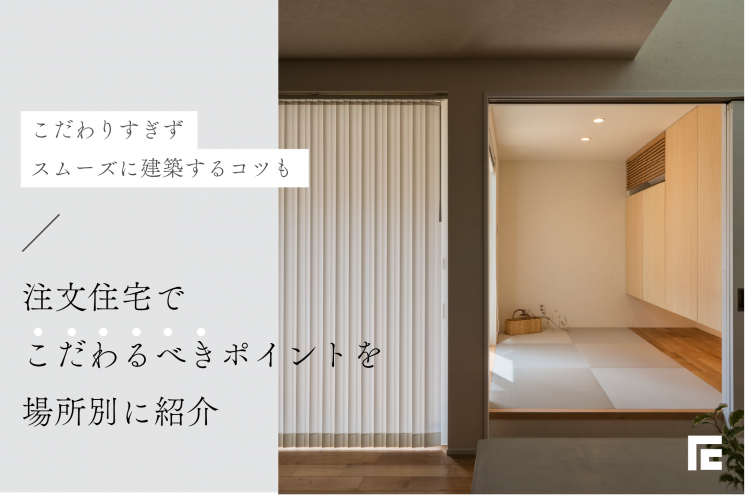費用・相場・ローン
注文住宅の坪単価の計算方法は?価格表示の注意点やポイントも!
更新:2025.12.02 公開:2025.10.17
注文住宅の費用を考えるうえで欠かせない「坪単価」。一見わかりやすい指標ですが、定義や計算方法はハウスメーカーや工務店によって異なり、見積額と差が出ることもあります。
この記事では、坪単価の基本や注意点を詳しく解説し、納得のいく家づくりのための判断材料を提供します。ぜひ参考にしてみてくださいね!
坪単価とは

住宅のチラシや不動産の広告でよく見かける「坪単価〇〇万円〜」という言葉は、建物の延床面積1坪あたりにかかる建築費を意味します。計算式はとてもシンプルです。
たとえば、建物本体価格が3,000万円で、延床面積が50坪であれば、坪単価は60万円となります。
坪単価を知ることで、家の価格を面積あたりで比較できるため、他の住宅とグレードや費用感をざっくり比較したいときに便利な指標です。
注意したいのは、坪単価の定義が業者によって異なる場合もある点。外構費や設備費が含まれていないなど、計算に含まれる内容はバラバラなので、あくまで「目安」として活用するのがポイントです。
坪単価と平米単価の違い
「坪単価」と似たような言葉で「平米単価(㎡単価)」というものもあります。「平米単価(㎡単価)」は、建物の延床面積1㎡(平米)あたりにかかる建築費を表したものです。
- 1坪=約3.3㎡
- 平米単価 = 建物の本体価格 ÷ 延床面積(㎡)
- 坪単価 = 平米単価 ÷ 0.3025(※おおよそ)
たとえば、建物本体価格3,600万円で延床面積が132㎡(約40坪)の場合、平米単価は「3,600万円 ÷ 132㎡ = 約27万円」、平米単価を坪単価に換算すると「27万円 ÷ 0.3025 = 約89万円」となります。
不動産広告では「㎡表示」が義務づけられているため、まず平米単価を確認し、平米単価を元に坪単価へ換算するという流れが一般的です。
どちらも面積あたりの建築コストを把握するための指標ですが、広告では坪単価、契約書などの書類では平米単価と使い分けられることが多いため、両方の意味と違いを理解しておくと安心です。
坪単価の計算方法

家づくりを考えるとき、「この建物は高いのか安いのか?」を判断するのは簡単ではありません。そのようなときに役立つのが「坪単価」という指標です。
坪単価を知ることで、建物の価格を面積あたりで把握でき、他の住宅と比較しやすくなります。
坪単価の計算方法は次の3つです。
- 計算式にあてはめる
- ExcelやWebサイトを活用する
- 平米単価から坪単価を計算する方法
ここからは、実際に坪単価を計算する方法を詳しく紹介します。
計算式にあてはめる
坪単価は、家の建築費を比較するうえでとても便利な指標です。以下のようなシンプルな式で求められます。
たとえば、家の本体価格が2,000万円で延床面積が50坪だった場合、2,000万円 ÷ 50坪 = 坪単価40万円 となります。
注意が必要なのは、坪単価に坪数をかけたからといって、家の総費用が出るわけではないということ。
坪単価で計算されるのは、あくまで「本体価格」の目安です。実際には、外構工事費や諸経費などもかかるため、総費用は本体価格より高くなります。
一般的に、本体価格は総費用の約75%とされているので、逆に「本体価格 ÷ 0.75」でおおよその総費用を見積もることもできます。
簡単に計算してみたいときは、このような計算式にあてはめてみると便利ですよ。
ExcelやWebサイトを活用する
坪単価や平米単価を効率よく計算したいときは、ExcelやWeb上の計算ツールを活用するのがおすすめです。たとえば、Excelでは以下のような関数を使えば、数値を自動で換算できます。
坪数を平米(㎡)に変換する場合 = 坪数 × 3.30578
平米(㎡)を坪数に変換する場合 = 平米数 ×0.3025
坪単価や平米単価を計算する式をセルに入力しておけば、入力するたびに自動で換算されるため、複数の住宅プランやハウスメーカーの比較にも便利です。
また、インターネット上には、坪から平米への換算や坪単価の自動計算ができる無料ツールも多数あります。計算方法を毎回思い出さなくても、必要な情報を入力するだけで簡単に数値が得られるので、Excelが苦手な方にも安心です。
「ざっくり比較したい」「手間をかけたくない」という方は、こうしたデジタルツールを上手に使いこなすことで、家づくりの情報整理がグッとラクになります。
平米単価から坪単価を計算する方法
不動産広告や建築資料では、面積が「平米(㎡)」で表記されていることが一般的です。そのため、「坪単価」で比較したいときは、平米単価から坪単価に換算する必要があります。
換算の際に使うのが、1平米 = 約0.3025坪 という変換係数です。坪単価を求めるには以下の計算式を使います。
たとえば、平米単価が27万2,000円だった場合、272,000円 ÷ 0.3025 ≒ 899,173円。坪単価としては約90万円となります。
このように、平米単価がわかれば、簡単に坪単価に換算できるため、異なる資料やハウスメーカー同士の比較にも役立ちます。
「どっちのプランが割安なのか?」を判断したいときは、平米単価から坪単価を計算する計算方法をぜひ活用してみてください。
坪単価の計算方法や価格表示の注意点

注文住宅を検討する際に多くの方が目にする「坪単価」という言葉。広告や見積書などで比較の目安にされがちですが、実はその「坪単価」は一見わかりやすいようで、思わぬ落とし穴が潜んでいることも。
正しく理解せずに坪単価だけで判断してしまうと、最終的な支払額や家づくりの満足度に影響を及ぼすことがあります。
坪単価の計算方法や価格表示の注意点は次のとおりです。
- 坪単価の算出方法には一定のルールがない
- 施工床面積と延床面積
- 本体価格と坪単価の関係
- 建物が小さくなると割高になる
順にみていきましょう。
坪単価の算出方法には一定のルールがない
「坪単価」という言葉はよく使われますが、実はその算出方法には明確なルールが定められていません。特に注文住宅の場合、ハウスメーカーや工務店ごとに計算基準が異なるのが実情です。
たとえば、本体価格に含まれる範囲が会社によって異なったり、延床面積のカウント方法にも違いがあったりします。そのため、広告や見積書に記載されている坪単価だけを見て「安い」「高い」と判断するのは危険です。
一方、マンションなどでは景品表示法に基づく公正競争規約が設けられており、比較的統一されたルールのもとで表示されています。そのため、マンションの坪単価は比較しやすい傾向にあります。
注文住宅では「何が含まれている坪単価か?」を確認することが重要です。坪単価の数字だけにとらわれず、内容を見極めましょう。
施工床面積と延床面積
坪単価を正しく理解するには「どの面積を使って計算しているのか」を確認することが大切です。住宅会社によっては、延床面積ではなく「施工床面積」を使って坪単価を計算していることがあります。
延床面積とは、建物の各階の床面積を合計したものです。ただし、玄関ポーチ・ベランダ・吹き抜け・クローゼット・地下室などは含まれません。
一方で、施工床面積には、延床面積に含まれない部分も加えた面積が含まれます。つまり、施工床面積の方が広くなるのが一般的です。
同じ本体価格であっても、どちらの面積を使うかで坪単価は変わります。
たとえば、本体価格が2,100万円で
- 延床面積30坪 → 坪単価70万円
- 施工床面積50坪 → 坪単価42万円
このように、見かけの坪単価が安くても、施工床面積で割っているだけというケースもあるのです。
坪単価の比較をするときは、「延床面積基準なのか?施工床面積基準なのか?」を必ず確認するようにしましょう。知らずに比較してしまうと、実際の予算感にズレが生じることもあります。
本体価格と坪単価の関係
注文住宅を建てる際の費用には「土地代」以外にもさまざまな項目が含まれます。主に必要となるのは以下の3つです。
- 本体工事費(建物そのものの工事費用)
- 別途工事費(エアコン・照明・外構など)
- 諸費用(登記費用、火災保険、住宅ローン関連費など)
このうち、坪単価の計算に使われるのは通常「本体工事費」です。本体工事費には、基礎工事・外装工事・内装工事・給排水などの設備工事が含まれます。
注意したいのが、会社によっては別途工事費や諸費用を含めた金額を本体価格として坪単価を出しているケースがあるという点です。
例えば、以下のような違いがあるとします。
- A社:本体価格2,000万円+その他の費用500万円
→坪単価 = 2,500万円 ÷ 50坪 = 50万円 - B社:本体価格のみ2,000万円で計算
→坪単価 = 2,000万円 ÷ 50坪 = 40万円
見B社の方が安く見えますが、実際は500万円の追加費用が別でかかるため、総額では変わらない、あるいはA社の方が割安ということもあり得ます。
そのため、坪単価だけで判断せず、「本体価格に何が含まれているのか?」を必ず確認することが大切です。見積書や営業担当に内容を確認し、後悔のない家づくりにつなげましょう。
建物が小さくなると割高になる
注文住宅では、建物の面積が小さくなるほど坪単価が高くなる傾向があります。その理由は、家の広さが変わっても、キッチンや浴室、トイレといった必須設備の設置コストはほとんど変わらないためです。
面積が小さくなると、そうした設備にかかる費用が床面積に対して占める割合が高くなり、結果として坪単価が割高になります。
たとえば、延床面積が50坪から30坪に減れば、総額の工事費は下がるかもしれませんが、1坪あたりのコストは逆に上がることがあります。
また、延床面積は「建物の各階の床面積の合計」を指し、建築面積(建物を真上から見たときの外周で囲まれる面積)とは別物なので、混同しないよう注意が必要です。
坪単価が高い=割高とは限らないという点もポイントです。数字だけで判断せず、その建物で理想の暮らしができるかどうかを重視することが大切です。
注文住宅で坪単価を抑えるための3つのポイント

注文住宅を検討する際「坪単価がどのくらいか」は多くの方が気にするポイントのひとつです。ただし、安いことだけを追い求めてしまうと、あとから「思ったより高くついた」「納得のいかない仕上がりになった」といった後悔につながることも。
大切なのは、費用を抑えつつも、自分たちの理想や暮らしやすさをしっかり実現する家づくりをすること。注文住宅で坪単価を抑えるためのポイントは次のとおりです。
- どんな計算式に基づいて計算されているか確認する
- 一階と二階の床面積を同じにする
- 住宅の構造や工法によっても坪単価は異なる
ここからは、坪単価を無理なく抑えるために知っておきたいポイントを紹介します。
どんな計算式に基づいて計算されているか確認する
注文住宅の「坪単価」は、一見するとシンプルな数字に見えますが、その裏には住宅会社ごとの独自の計算基準が存在することが多くあります。坪単価を比較する際には、どんな計算式や面積基準で算出されているのかを必ず確認しましょう。
たとえば、同じ建物でも「延床面積」で割った場合と「施工床面積」で割った場合では、坪単価の見た目が異なります。
施工床面積には、ベランダや玄関ポーチ、吹き抜けなど延床面積に含まれない部分も入るため、面積が広くなって坪単価は一見安くなるのです。
また、坪単価には塀や庭などの外構費用、ローンの手数料、登記費用、税金、地鎮祭・上棟式などの諸費用は含まれないのが一般的です。こうした諸費用はすべて別途発生する費用であり、見積もりを確認するときには注意が必要です。
坪単価の「安さ」に惑わされず、その価格の内訳や含まれていない費用まで把握したうえで、総合的な予算で判断することが大切です。
疑問があれば、遠慮なくハウスメーカーや工務店に質問し、納得したうえで契約に進みましょう。
一階と二階の床面積を同じにする
坪単価を抑えたいと考えるなら、建物の形状や構造をできるだけシンプルにすることが効果的です。なかでもおすすめなのが、一階と二階の床面積を同じにする設計です。
住宅は、凹凸の少ない正方形に近い形ほど構造が安定しやすく、工事も効率的に進められるため、無駄なコストがかかりにくくなります。
一階と二階の面積を揃えることで、柱や壁の配置が効率化され、構造材の使用量も抑えられるため、結果的に坪単価が安くなる傾向があります。
一方、平屋建てはワンフロアで完結する分、基礎部分や屋根の面積が広くなり、工事費用が割高になることも。
特に基礎工事は、安全性に関わる重要な工程であり、面積が広いほどコストがかさみます。コストとデザインのバランスをとるためにも、建物の形状や階数の設計は慎重に検討することが大切です。
住宅の構造や工法によっても坪単価は異なる
坪単価は、間取りやデザインだけでなく、住宅の構造や工法によっても変わります。構造とは、建物の骨組みとなる部分のことで、一般的には以下の3つに分類されます。
- 木造:最も一般的で、コストも比較的安価
- 鉄骨造(S造):木造より耐震性・耐久性に優れるが、そのぶんコストは高め
- 鉄筋コンクリート造(RC造):耐火性・耐久性・防音性に優れるが、構造が重厚なため坪単価は高め
たとえば、国税庁「地域別・構造別の工事費用表(1m2当たり)【令和6年分用】」によると、構造別による坪単価の全国平均は
- 木造:約68.4万円(20.7万円/㎡÷0.3025)
- 鉄骨造(S造):約97.2万円(29.4万円/㎡÷0.3025)
- 鉄筋コンクリート造(RC造):約100.5万円(30.4万円/㎡÷0.3025)
となり、構造が変わるだけで坪単価に数十万円の差が出ることがわかります。
さらに、「工法」=構造の組み立て方によっても価格は変動します。たとえば、木造でも在来工法とツーバイフォー工法では工事の進め方が異なるため、材料費や人件費が変わるのです。
家づくりの費用を左右する要素なので、希望する構造・工法がどれに該当するのか、坪単価にどう影響するのかを確認することが大切です。
坪単価を抑えるためではなく、納得のいく家づくりを行いましょう

ここまで、坪単価の計算方法や注意点について解説してきました。坪単価は家づくりの費用感をつかむための大切な指標ですが、金額の大小だけで判断するのはとても危険です。使用されている面積の基準や、何が費用に含まれているかによって、見た目の数字は変わります。
本当に大切なのは、「その家で自分たちらしい暮らしができるかどうか」という視点です。
見た目の価格に惑わされず、納得のいく住まいを実現するためには、信頼できるパートナーと一緒に計画を進めることが重要です。
グランハウスは岐阜/愛知/三重で注文住宅を提供している設計士集団です。
「ハウスメーカーでも工務店でもない、設計士とつくる」からこそ、お客様の想いやこだわりに丁寧に向き合い、ちょっとカッコいい、暮らしやすい家をご提案します。
施工実績は1,000件以上。「より良い家づくりをしたい」「岐阜で注文住宅を建てたい」とお考えの方は、ぜひグランハウスに一度お問い合わせください。